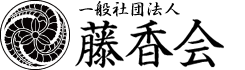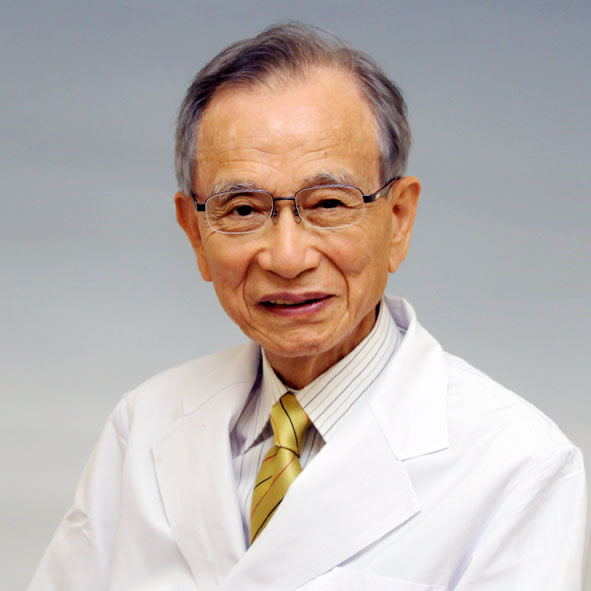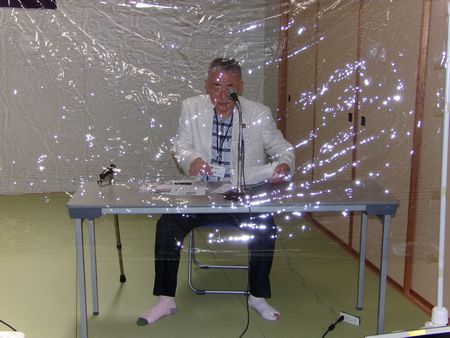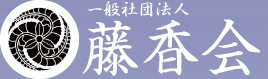11月10日、史跡巡りを実施しました。肌寒い中を会員および家族44名の参加でした。コロナ禍の中で「三密」を避けるため、2台のバスにそれぞれが間隔を開けて着席して、時刻をずらして出発しました。
「令和」の起源となった太宰府の坂本八幡宮では会員の岡部定一郎さんから「令和の教え」として暦の話があった。持統天皇が、一年をいくつかに区切り、それぞれに節供(節句)を決めて、人々の安寧を祈ったことなどを話された。


古心寺では渡辺桂堂住職が秋月種雄から16代続いて、黒田家に代わったこと、秋月家は日向高鍋に移り、そこから上杉鷹山などの名君が出たことなどを話された。古心寺は大徳寺の江月和尚により山号を長政公の法号から「興雲山」と命名され、代々大徳寺から住職を迎えている。

黒田家墓所では秋陽会事務局長の吉田長利さん(本会々員でもあります)から歴代藩主や室のお墓について説明がありました。

隣にある大涼寺は初代長興公の母の法号から命名されている。

秋月の史跡巡りを終えて八丁トンネルを抜けて嘉麻市大隈にある麟翁寺を訪問。住職の話では母里太兵衛は高い身長で筋肉質の人であったことが甲冑から推測されるとのこと。また「母里(ぼり)」は当時の方言かなまりでこれを「もり」または「もうり」と発音していたことから幕府が感状を出すに際して「毛利」としたことで、幕末まで毛利姓を使い、明治になって元の「母里」に変えたことなどの説明があった。樹齢500年にもなるクロガネモチの側の母里太兵衛とその子、孫が並ぶ墓所を参拝した。



小石原に移って、太田和孝さん(本会々員)のマルワ窯を訪問、会員の一人ひとりにご飯茶わんを頂戴した。高取焼宗家では宗家の夫人高取七絵さん(本会々員)から、釉薬の甕、昇り窯、唐臼、粘土を作る水簸等の説明を受け、全て自家で作る由。その後、歴代の逸品の茶碗、茶入れ等が並ぶ部屋で、会員全員がお菓子とお抹茶の接待を受けました。





朝倉の円清寺は曹洞宗のお寺で栗山善助(大膳の父)が開基となっている。山号、寺号とも如水公の法号から「龍光山円清寺」ということ等が住職から説明された。